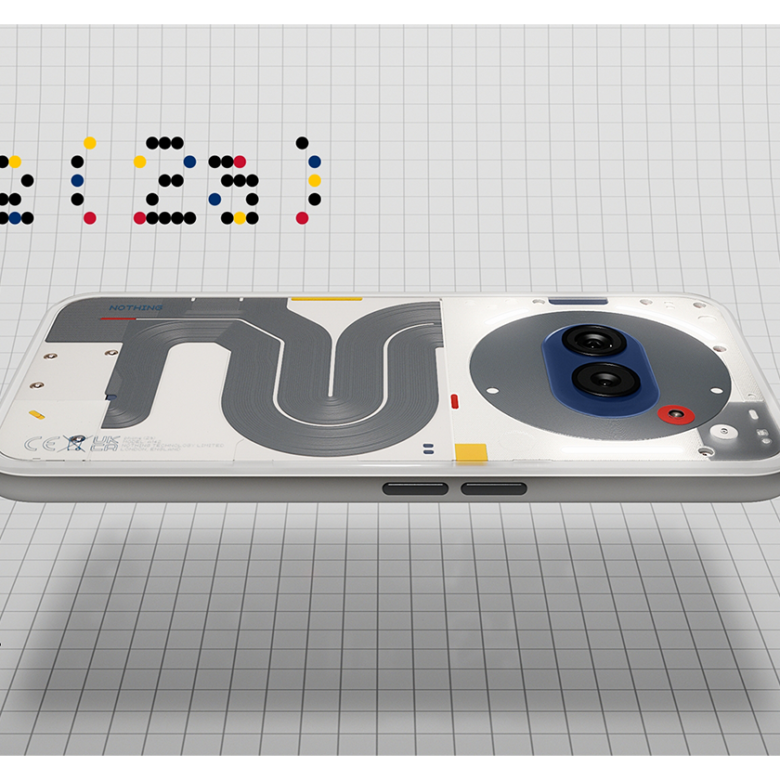ファッション史はファンタジーではなく、現実。20代の私が見る「ファッション イン ジャパン 1945-2020 ─流行と社会」


現在、国立新美術館で開催中(9月6日まで)の「ファッション イン ジャパン 1945-2020 ─流行と社会」は戦後日本におけるファッション史を巡る多角的かつ包括的な回顧展となっている。本展最大の特徴は、戦後日本におけるファッションの軌跡および社会的背景とともに、デザイナー(発信者)と消費者(受容者)の双方向の目線から捉えているということではないだろうか。
この「ファッション イン ジャパン 1945-2020 ─流行と社会」についてライターのkozukarioがレポート。本展の序章となるプロローグ「昭和初期〜1945年」から第8章「未来へ」まで各章の個人的見どころを紹介する。
ファッション史はファンタジーではなく、現実
まず、1970年代に高い評価を得た髙田賢三や三宅一生、80年代、世界に黒の衝撃を走らせた川久保玲と山本耀司など、日本のファッション史は、その史上に名を刻む彼らの存在を起源として語られることが多い。しかし、この世のほとんどの出来事に因果関係があるのと同様、ユニークなデザイナーらの出現も突発的なものではない。日本のファッションも時流とともに成長してきたものであり、デザイナーによって流行が出来た時代もあれば、消費者によって形成されたムーブメントもある。
そして主に戦後日本のファッションを考察する8章で構成されている本展は、和装と洋装が並列していた戦前・戦中1920〜1945年の日本のファッションを取り扱うプロローグから始まる。「戦後の日本ファッション史」にフォーカスするには、1945年以前の日本におけるファッションへの言及も当然ながら必須なのである。このように、どのようなスタイルも突如表出したものではなく、時の流れとともに成長、もしくは変遷してきたものであるということは明らかだろう。
私が本展に入場したのは土曜日の15時、退場したのは18時過ぎだった。3時間以上4時間近く会場に滞在していた私はそのほとんどの時間、半べそをかいていた。これは私の感受性が特殊なわけではない。この「ファッション イン ジャパン 1945-2020 ─流行と社会」では、現代、我々が目にする・手にする・纏う服が、歴史という層の上に重ねられた表層であることを身に染みて知ることができる。自分が生まれた時代の豊かさや既知の事実に付随する未知の事実を知ること、そしていつも液晶越しに見ていた作品が数十センチ先にあることに感動して泣けてくるのである。
プロローグ:戦前・戦中・戦後(第二次世界大戦)

第二次世界大戦という出来事やそれが勃発する以前から世界というものが存在していたことは誰もが知っている事実だが、そこにどのようなファッション史が築かれてきたのかということを知らない人は多くいるのではないだろうか。私もその一人だった。
戦時中、衣生活の合理化・簡素化を目的として法制化された「国民服」の文化が、戦後日本のファッションの洋装化に影響しているという。「国民服」が男性の標準服となったことにより、戦前の「モダンガール」にも見られる洋服と和服を混成する独特なスタイルから、洋服のみを日常の服とする文化が発展するきっかけとなった。また、女性については「婦人標準服」よりも「もんぺ」を日常的に着ることが一般的であった。「もんぺ」が空襲時の防空用に着用を義務付けられていたと知っていたために、戦時中のものが目の前にあるというだけで涙がこぼれそうになる。グレー地にネイビーで唐草模様が描かれていた。先染め織物である銘仙は、戦時中という厳しい状況下でもモダンなデザインを積極的に取り入れていた。日本人が持つファッションへのひたむきな関心がうかがえる展示だった。
第1章/第2章:日本の誇りとモダンへの先進

第1章では1945〜50年代、第2章では60年代の様子が展開されていた。戦後の物資不足の影響から多くの女性が洋裁を学んだという。それがそのまま50年代の洋装ブームへと繋がる。日本で最初にファッションショーを開催したデザイナー田中千代のスーツや、女子美術洋裁学校を開設した伊東茂平デザインのジャケットやスカートは、洋裁の技術が発展したこの現代に見てもよりモダンで、洗練されたものだと感じた。
日本のファッション・イラストレーターの草分け的存在である長沢節によるスタイル画を見るやいなや、エゴン・シーレの作品を思い出す。足がすらりと長く、骨ばった細い体に長沢節が宛がった洋服はどれもスタイリッシュで60年以上に描かれたとは思えないほどモードで「いかすかっこ」だった。

1950年代後半の映画黄金期、400本にものぼる映画の衣装を手掛けたという森英恵のドレスの展示も印象的だった。
1965年にニューヨーク・コレクションに初参加した森英恵の作品は、浮世絵が描かれたチュニックや和装を想起させるまるで着物のようなジャケットなど、日本の伝統文化が反映されているように思う。日本のクラシカルで伝統的な装いと、未来への期待を込めた新感覚のファッションを世界へ発信したアジテーターとなった。
第3章:世界に頭角を現す日本人デザイナー山本寛斎

第3章では1970年代に登場したコシノジュンコ、髙田賢三、三宅一生、山本寛斎など「個性豊かな日本人デザイナーの躍進」を取り上げる。「ファッション イン ジャパン 1945-2020 ─流行と社会」の広告を見て、多くの人が待望としているのはこの章ではないだろうか。
かの有名な山本寛斎の《トーキョーポップ》(1973) が展示されているのはこの章である。
1967年に栄え有る装苑賞を受賞した山本寛斎は、その4年後の1971年、ロンドンにおいて日本人として初めてファッション・ショーを開催。自身の舞台を世界へと広げたデビューコレクションでは、歌舞伎のストーリーやビジュアルに触発された作品群を披露した。既製服の大量生産が可能となり、洋服が購入するものへと変化したことにより若者は流行に敏感になっていた。これは1964年の東京オリンピックを機にカラーテレビが普及したことも関係している。それも相まって、当世の常識を激しくブレークスルーするアヴァンギャルドな山本寛斎のデザインは、流行の最先端を行く若者から絶大な支持を得た。
《トーキョーポップ》は初めてアメリカでコンサートを行うデヴィッド・ボウイが、ステージ衣装として山本寛斎にデザインを依頼した際の一着である。2枚の扇のようなパンツを特徴とする黒いジャンプスーツで佇むボウイの姿は世界中に衝撃を与えた。今は亡き山本寛斎とデヴィッド・ボウイがフィッティングするその様子を想像させる一等品。若き2人の希望が展示から満ち満ちていた。
第4章:各々の哲学・思想論。TAKEO KIKUCHIのパッション

1980年代に日本国内で広く社会的なブームとなった「DCブランド」を深く紹介するのが第4章。当時、既に流行発信地となっていた東京の青山・原宿・渋谷から広がったDCブランドブームは、バブル時代(1985年から1991年)の象徴ですらある。
第4章で我々を出迎えるのは、1982年パリで黒の衝撃を轟かせた川久保玲のCOMME Des GARÇONSの1983年春夏と秋冬コレクション。JUNKO KOSHINOやYUKI TORIIと、そうそうたる顔ぶれが自身のブランド哲学を語るべく悠然と並んだ。一室に集合しているにも拘らずそれぞれのブランドの前で足を止めその世界観に没入せざるを得ない。DOVER STREET MARKETに似た構造をした会場だと感じた。
最も衝撃的だったのはTAKEO KIKUCHIの展示。トラディショナルかつソフィスティケートな印象の英国風スタイルのブランドであるというTAKEO KIKUCHIに対する私の固定観念は宙にふわふわと浮かび、呆気に取られてしまった。1986年秋冬の最後のコレクション・ピースと、それにインスパイアされた2015年のコートが並んでいた。誇張されたディテールと大胆なカットワーク、仰々しいほど派手な装飾を見て「菊池武夫の作品だ」と誰が想像できるだろう。菊池武夫の男らしさというか、ファッションへの熱誠に惚れ惚れしてしまった。
第5章:DCブランドの派生のようで一線を画しているような若者文化

A BATHING APE®のエイプカモ(カモフラ柄)が入口で垣間見え、涙ぐむまいと唇を噛みしめて鑑賞していたことで低下しつつあった体力が一気に回復してきた。
さて、嬉しいことにやっと私が生まれた1990年代へ突入。第5章では「渋谷・原宿から発信された新たなファッション」ストリートファッションが紹介されている。消費者である若者が主体となって新たなファッションを発信していたハツラツとした時代だ。
「藤原ヒロシ2号」ことNIGO®のA BATHING APE®と、「ジョニオ」こと高橋盾のUNDERCOVERの仲良しコンビがお出迎え。ファッション・デザイナー、ミュージシャンで「キング・オブ・ストリート」の愛称で知られる藤原ヒロシらとの交友関係などから、80年代のDCブランドとは異なるスタイルの若者文化が育まれたといえる。
ストリートファッションはパンクやヒップホップといった音楽や、スケートボードなど周辺文化とも大きく融合している。しかし、思い返せば音楽とファッションの融合に成功を齎したのは、デヴィッド・ボウイと山本寛斎ではないだろうか。本展には「歴史の上に今がある」ということを強く意識させられる。
第6章:個性と没個性(ゴスロリとユニクロ)は表裏一体か

「ゴシック」や「ロリータ」など「kawaii」が原宿から世界へと溢れ出した00年代は、誰もがファッションを通してアイデンティティを示した。好きなものを好きなだけ盛り込んだ「kawaii」ファッションは日本が世界に誇る新しい文化となる。
一方で、出口の見えない不況の影響を受けて、手軽なプライスラインのファストファッションも日本中に浸透していく。低価格にも関わらず、デザイン性に富んだファストファッションの普及により誰でも人気のスタイルを実現することが可能となった。「ゴシック」や「ロリータ」と、没個性的なユニクロの《ヒートテック》が会場のワンルームを共有していたことが印象深い。
ファッションとは?個性とは?
ということを狭く深く、時に広く浅く、日本人が考えることが増えたのは第6章で展開された2000年代、この頃からではないだろうか。
第7章:自分らしさを追求しよう。私のスタイルいいね、あなたもいいね!

00年代におけるファッションを通した自己探求は、第7章の10年代「いいねの時代」へフェードインする。
もう2010年代になると「他人は他人、自分は自分」という価値観が日本列島に充満し、SNSでは誰もが自身のスタイルを披露する。千差万別の色・形・素材から成る洋服たちの展示を見て、朝日新聞のロングインタビューで川久保玲が話した「ファッションとは、それを着ている人の中身も含めたものなのです」(2012年1月19日掲載)という言葉を思い出した。まさにモードな発言だ。
私個人としては、AKIKOAOKIが見れたことが本当に嬉しい。デザイナーの青木明子は幼稚舎から高校まで一貫校に通っており、学校指定の制服を着て登校していた。AKIKOAOKIに付き纏う「ユニフォーム」というキーワードは制服に由来しているはずだ。会場には2018年秋冬と2020年春夏の作品が展示されていたが、どちらにも共通する所感として、フォーマルな装いであるユニフォームを斬新なディテールで再構築しているように目に映った。いいね!
第8章:ファッションの新しいサーカディアンリズム

SNSによって都市と地方、日本と世界はみるみるうちに距離を詰めていく。新型コロナウイルスのパンデミックを受けてもなお発信と受信は止め処なく加速を続け、ウェブで何でも手に入る現代。
そんな現代のファッションにフォーカスした最終章第8章のタイトルは「未来へ」。我々は前古未曾有の緊急事態の最中、未来に目を向けることとなる。本章において、大量消費が当然の行為となった現代のファッションを見ると、その社会性とは裏腹にサステナビリティを重視したアイテムや、エシカル消費への傾向が見られる。ジェンダーの概念も再検討されるなど、様々な分野の社会問題において既存の価値観の比較検討が織り成され、ファッションが導き出す問答を探っている。
ヴァージニア・ウルフの小説『オーランドー』をテーマに掲げたCOMME Des GARÇONSのノンバイナリーなコレクションや、どのような体型にも似合うISSEY MIYAKEのボディポジティブなプリーツ、ユニクロのリユースプロジェクト「RE.UNIQLO」に、使用済みのパラグライダーをリユースしたTHEATRE PRODUCTSのアップサイクルバッグ「HOZUBAG」などがラインナップ。

トップ、パンツ、靴下、ブーツ│川久保玲│コム デ ギャルソン│2020年春夏│京都服飾文化研究財団
ボディス、スカート│川久保玲│コム デギャルソン│2020年春夏│京都服飾文化研究財団
生活必需品であるファッションは単なる生活必需品ではなく、デザイナー(発信者)と消費者(受容者)の表現の手段でもある。しかし安価だからという理由で消費されるものもあれば、普段使いでなくとも何か目的(友達の結婚式に着ていくドレスとか、成人式の振袖とか、ハレの日)を達成するため必要に応じて購入されるものもある。
「ファッション イン ジャパン」に、多角的にアプローチする展覧会「ファッション イン ジャパン 1945-2020 ─流行と社会」。1945年の戦後、いやそれよりももっと前から現在まで、糸でファッション史を紡いできたのは我々人間である。未来へ向って私達は糸を紡ぎ続けるのだろうか。はたまた糸ではないかもしれない。これが現実である。
Photos : Ken Kato