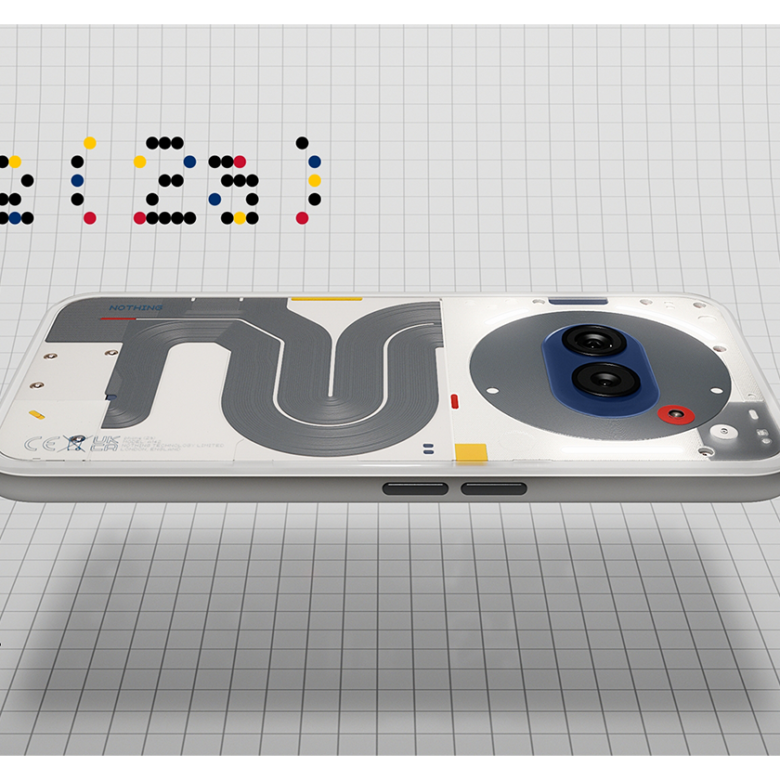映画「モザイクストリート」にできて、日本映画にできないもの。

あなたの考える日本人とは?
日本を代表する映画のキャラといえば、「男はつらいよ」の寅さん、昭和任侠シリーズなどの高倉健さんが思いつく。あるいは、世界で活躍するケン・ワタナベ(渡辺謙さん)が演じるような役も、きっと立派な日本人像なのだろう。そして、2022年現在、海外から演技はインフルエンサー並みだ、と批評されるアイドルを起用した学園物や、人気コミック原作、アニメが圧倒的なシェアをしめる邦画界で、正しい日本人像はどうなっているのか、考えてみたいのだ・・・そんなイントロを当初、考えていた。しかし今まさに映画業界に激震が走っている。連日の報道でみなさんもご存知のとおりだ。
いや、正確には今までも、こうした訴えは度々あった。セクハラやパワハラを受けた被害者の悲痛の声を、その業界の権力者やその恩恵に預かるものたち、そして多くの「中立」と謳うマスコミや、匿名の一般人たちによって圧殺されてきた。昨年、自らのインスタグラムで、芸能界の先輩である島田紳助氏や出川哲朗氏などからのセクハラ被害を訴えたモデルさんの件は、特に記憶に新しい。
翻ってハリウッドで、#metooムーブメントが巻き起こったのが、2017年のこと。日本でも数年遅れではあるが、このムーブメントに似たことが始まっている。
映画というアートについて語るこのコラムで、今この問題について語らないというのは、今後さらなる暴力、犯罪そしてさらなる被害者を増やすことに加担するのと同じこと、という思いのもと、今回は問題提起する。
今話題になっている、園子温氏や、映画「ヘドローパ」制作スタッフなどによる撮影現場での暴力的な酷い演出、怒号、命令、また業務外の場での、強制、暴力、レイプ、などの行為は、犯罪であり、奴隷と同じ類の人権侵害だ。そして、この映像業界に流れる伝統的な「空気」を正そうとしない製作会社(出資者や製作委員会)や運営組織、メディアも同罪である。被害者の立場から見れば、沈黙は、中立、静観ではなく、非合法行為の黙認とみなされるからだ。
Japan Film Projectより、被害アンケートなるものも公開されているので、心当たりのある匿名希望者は、ぜひご覧ください。
https://jfproject.org/
社会的少数者の話
こうした直接的な被害もさることながら、もっと根深い問題もある。日本映画界でのマイノリティの活躍とその障壁についてである。
そもそも日本におけるマイノリティとはどういう人たちを差しているのか。「日本は単一民族の国家である」という暴言をはいた政治家もいる。21世紀にもなって、仮にも先進国のトップ層がこういう発言を堂々としてしまう程度に、日本人はマイノリティへの意識が、低いのが現状ではないのか。
マイノリティ=社会的少数者(しゃかいてきしょうすうしゃ)とは、その社会の力関係によって、少数者、少数派もしくは弱者の立場に属する者やその集団を指す。(wikipediaより)
ここでいうマイノリティ=社会的少数者とは、単に人口に対して多い少ない、の話ではなく、社会システムの都合上、「後回し」にされてきた人たちのことを指す。女性や子どもをはじめ、何らかの障害を持つ人、一人暮らしの高齢者、LGBTQ+、先住民、移民、難民、その子孫たちが暮らす多民族・多様性国家、それが現代日本の姿のはずだ。社会学的な論説は専門家の方々に任せるとして、ここでは映画の表現に絞って語っていきたい。
日本映画界は、マイノリティをどう見てきたのだろう。
ちなみに、英語では最近「男性」「女性」のどちらにも属さないと自認する、「ノンバイナリー」の人たちの三人称単数を、He/Sheをやめて、「They」とされるようになった。日本語では、彼ら、彼女ら、そのどちらにも属さない自己認識を持つ人たちの三人称単数はどう呼ぶべきなのか、の論争があまりなされていないような気がするが、このコラムでは「マイノリティの人たち」で統一する。
映画で描かれたマイノリティ
歴史を振り返っても、マイノリティを描いた邦画作品は本当に数少ない。まず頭に浮かぶのは、在日朝鮮人の若者のリアルを描いた井筒和幸監督の「ガキ帝国」(1981年 ATG)だが、wikipediaをチェックしてみると、その続編では「在日朝鮮人は出すな」とか、「名前を日本名にしろ」といった不当な指示があったと、驚愕の裏話を知ることができる。一般社会におけるマイノリティへの扱われ方が良くわかるエピソードだ。
(これが事実でないのであれば、東映から訂正のリリースがあるはずだが、公式サイトにはそれらしいリリースはなし。)
さらに遡って、今から約60年前、昭和34年(1959年)に制作された「キクとイサム」(今井正監督)という作品。戦後日本の人種差別を描くこの作品には、当事者と同じエスニックルーツであるアフリカ系ハーフの子役俳優が起用されている注目すべき作品だ。当時、日本にもミックスルーツの子どもたちが多く存在し、社会から疎外、差別されていたことをこの作品から窺い知ることができる。今井監督は、実際その役柄と同じ属性を持つ子役をオーディションし、自ら演技を仕込んだ、という熱いエピソードが公式サイトに載っている。
すべての作品をチェックはできないが、どれもマイノリティの存在は、ほぼタブーのような扱い、差別の対象として描かれてきたといってよいだろう。

日本人の表象とは?
「表象」という言葉を聞いたことはあるだろうか?
マイノリティ当事者が、自分と同じ属性を持つ役柄を演じることを、その当事者を表象するという。映画で描かれている日本のマイノリティについての現状を語るにあたり、まずはこうした聞き慣れない用語のチェックもしておきたい。
恥ずかしながら、筆者は現役ハリウッド俳優の松崎悠樹氏のtwitterで、初めてこの言葉を知ったのである。英語ではRepresentationという。WEBの辞書で引くと、
[名](スル)
1 象徴。シンボル。また、象徴的に表すこと。
2 哲学・心理学で、直観的に心に思い浮かべられる外的対象像をいう。知覚的、具象的であり、抽象的な事象を表す概念や理念とは異なる。心像。
表象とは、「対象となるものを表す具体的なイメージ」のことと解釈する。「キクとイサム」で主演を演じた二人の子役はまさに、当時者を表象していたことになる。
プログレス・プライド・フラッグ
さらに多種多様なマイノリティの中のマイノリティを包摂するためのプログレス・レインボー・フラッグ
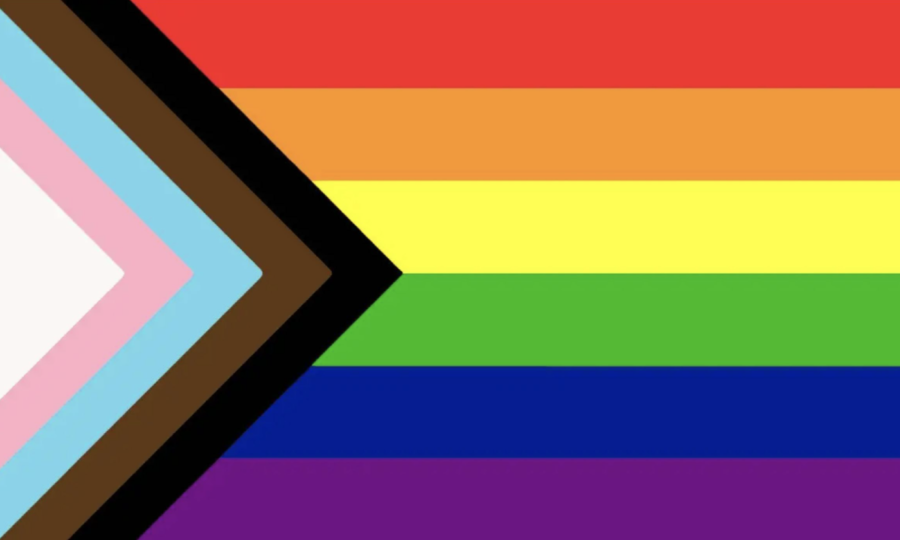
さらに、差別や偏見にさらされやすい、マイノリティの中のマイノリティを指してQTBIPOCと呼ぶことがある。これはQueer(クイア) and Trans(トランスジェンダー), Black(黒人), Indigenous(先住民), People of Color(非白人)の頭文字から取られている。こうした言葉を学ぶことによる、マイノリティへの認識を高めることも重要なことだと思う。
少数派の事実
21世紀も5分の1が過ぎた現代、映画界におけるマイノリティの描かれ方どうなっているのか。先出のすでに20年以上ハリウッドで活躍し、今まさに日本映画に蔓延る暴力や違法行為に対し、強烈な言論で風穴を開けている俳優松崎悠希氏の話を紹介したい。
彼を取材した記事によれば、トランスジェンダーなどのマイノリティの配役は、現状、一部の有名俳優やシスジェンダー俳優の「挑戦」とされていて、セールスに利用されている。本来であれば、トランスジェンダーの役者が演じるべきである場合も、そもそも配役の時点でそのチャンスが排除されているという。
松崎氏の主張の裏付けのために、試しにちょっと検索すると、確かにこのような記事はいくらでも出てくる。
では、当事者が演じるべき場合とは、どのような場合か?
当事者が演じなければならない理由
前述したように日本の映画では、マイノリティ役を表象する形での当事者の起用は極めて少ないケースだ。ここ数年、LGBTQ+の人たちの恋愛や苦悩を描いた映画は多くなってきているが、どの作品も話題性を狙い、実力派や旬の俳優の起用が多い印象だ。彼らの演技自体を論じることは少し筋が違うので別に譲るとして、ここで問いたいのは、果たしてそうしたマイノリティ役のキャスティングに、本来当事者たるべき俳優がその候補として検討されることがあるのか、という疑問だ。
実際、社会的マイノリティの表象を、当事者が演じる映画は増えてきている。ここに筆者が注目している作品をいくつか紹介したい。「片袖の魚」は失礼ながら未見なのだが、他の2作は、どちらも当事者による熱演を観ることができる作品で、たとえ演技を学んで間もない役者でも、観るものを圧倒し、感動させる力のある作品だ。
・アイヌの家に生まれ、伝統と自己のアイデンティティの間で葛藤しながら育つ少年を、大自然の中で描く「アイヌモシリ」
https://www.switchback.focalnaut.com/
・愛知県のおおぶ市で生まれ育つブラジル系2世を含む、多感なこどもたちの葛藤と心の成長を、さわやかに描いた異色作「スイッチバック」
・トランスジェンダーの役を当事者が演じる話題作「片袖の魚」
こうした映画に登場する移民2世、ミックスルーツを持つ人や、同性愛者、トランスジェンダーなどのテーマを取り扱う時、キャスティングにはその表象を完璧に演じることができる実力派俳優を起用する選択肢もある。例えば、「ギルバートグレイプ」で知的障害のある少年を演じた、ディカプリオのような俳優を起用する方が、作品の質が上がるのでは?という意見もあるだろう。その意見に意を唱えるものではない。
しかし、「片袖の魚」を制作した東海林毅監督は、「あえて当事者に演じてもらうことに重要な意味がある」という。
「例えば、シスジェンダーの男性がトランスジェンダー役を演じる映画を見た人は、トランスジェンダーの表象をその俳優を通した人物に重ねることになる。でもそれは、あくまでプロが演じた表象であり、現実とのギャップを常にはらむので、誤解されたイメージが流布する危険性があるんです。それでは、今までと何も変わらないですよね。」
東海林監督はさらに、マイノリティ当事者であり、俳優を職業とする人たちの雇用機会が失われる危険性についても指摘する。
「当事者以外の役者ばかりキャスティングすることで、当事者はそもそも競争に参加できず、いつまでもチャンスが掴めない。ただでさえ、その実体数が把握できないマイノリティ俳優たちは、映画界でのロールモデルを生み出すこともままならず、マイナーなままの悪循環が続く。」
この主張は松崎氏が言っていることとほぼ一致していて、非常に説得力がある。そして何より、マイノリティ当事者が演じることでのみ伝わる、深い感情表現があるのも確かだと思う。
余談ではあるが、今話題になっている「ゴールデンカムイ」実写化のキャスティングについて、アイヌ民族の俳優を起用するべきでは?という議論も、とても興味深いトピックだ。
以上のような文脈において、マイノリティの役を当事者が演じることは、日本映画界の未来にとって、極めて強い意味があるのだ。
映画、アートとして
本来アートは、社会に蔓延る無意識な傲慢さをあぶり出し、闇を照らす火矢を放つものであるべきだ。それと同時に、そうした傲慢なパワーから弱い者を守るかけこみ寺であるべきだ。
そこにはすべての人を受け入れる寛容さがあるべきなのだ。
映画市場では、興行性や最新技術のショーケースよりも、アートとしてのナラティブを追求した作品も市場に多く出回っているし、ジャンルとしても確立されている。大島渚監督、伊丹十三監督など、社会に強いメッセージを放つ作品が代表的だろう。
大島渚監督「戦場のメリークリスマス」では、坂本龍一とデビットボウイが演じる捕虜と日本兵の同性愛が描かれ、当時は衝撃作と話題になったが、これを見ていた当時のLGBTQ+当事者の中には、自らのアイデンティティを娯楽作品に搾取された、と感じる人もいたのではないだろうか。当時中学生だった筆者は、その性的タブーが全開にセールスされた「戦メリ」を見ること、そのイベント性に酔っていただけで、それを観た当事者が、どう感じていたのか、というところまで想像することなど到底できなかった。
しかし、たとえ過去に観て感動した作品も、今観ると、マイノリティや人種差別に無自覚なものもあり「これは酷い」と思える作品も少なくない。時代が変わったから?
否、我々が根本的な問題から目を背けていただけだ。問題は常にあった。それを証明する出来事もある。
1973年、「ゴッドファーザー」のドン・コルレオーネ役でアカデミー賞主演男優賞を受賞した時のマーロン・ブランド氏のボイコットについて、映画史に残っている手記がある。ブランド氏の手記によれば、「社会的マイノリティは、映画の中で意識的に、悪者扱いされ、虐げられ、殺されてきた。」
ブランド氏の訴えから50年が経ち、日本映画はどうだ?
「アイヌモシリ」や「スイッチバック」、「片袖の魚」のような作品は、今後増えていくと予想する。なぜなら、消費者がそういう作品を求めている傾向にあるからだ。これはマイノリティの役に当事者をキャストすることが、今どきのトレンドでしょうとか、気分的なものを頼りに言っているのではない。
- 学校教育でLGBTQ+をはじめとする「性の多様性」について教えるべきかを聞いたところ、「教えるべき」「できれば教えるべき」と回答した人は88.7%と大多数
- LGBTQ+層の消費パワーをはかる19カテゴリーの市場規模は5.42兆円(推計)
こうした資料をみるかぎり、当事者の友人や家族、海外ドラマで知識を得た「アクティブサポーター(アライ)」を含め、国内の社会的マイノリティ、LGBTQ+関係者の消費動向は、今後ますます高まりが予想される。つまり、社会的マイノリティを題材に描く映画は、より多くの人に受け入れられるようになり、それに従ってモノが売れる、つまり儲かる。
儲かるということは、興行的にも期待値が高まるわけで、そういった盛り上がりを見せる中で、日本映画、業界のスタンス、その意識が改めて問われることになる。
日本の多様性を代表するキャラクター
この国の多様性を語る時に、わかりやすい例は女子高生だ。ラノベ(ライトノベル)というジャンルが生まれて以降、その描かれ方の多様さは、異常なまでに進化した。「青春日本代表」と書かれた靴下を履いて、歌い踊るアイドルがアメリカで数万の観客を前にライブをする。これは多様である女子高生のロールモデルの一つの姿だ。女子高生の表象が、多様な姿で描かれるのと同じように、マイノリティの表象も多様であるべきで、描き方も進化していくべきである。
今後、マイノリティの人たちが俳優を夢みる未来に、どういうロールモデルの姿を提示できるのか。ここに、そんな未来を感じさせる1本の映像がある。

もし日本のドラマで マイノリティのキャラが「フツー」に登場し、その姿が日本中のお茶の間で流れたら・・・
「モザイクストリート」はそんなドラマを実際に体験して頂くために作りました。
(公式youtubeページより)
この作品に出演する俳優は、全員マイノリティだが(松崎氏曰く、ハリウッドでは彼もマイノリティ)、それを物語上で特別視しているわけではない。それぞれが作品の中で与えられた役を演じ、日英のセリフが入り乱れる、どこか近未来的で、独特な空気感のミステリー作品だ。画面に映る独特の重厚な光は、俳優たちをドラマの世界にごく自然に映し出し、観るものに緊張を強いる。10年後、いや3年後には、これが普通の感覚になっている、そんな希望が込められた作品だ。
プロデューサーでもある、松崎悠希氏は、
「マイノリティへの差別を描くだけでは、マイノリティの方々の社会進出にはならないんです。社会で受け入れられるということにはつながらないんですよ。すでに受け入れられた後の世界を実際に見せてあげて、視聴者がその状態が「普通」だなと感じるようにしてあげないといけない」と語る。
この作品の根底に流れる、重要なメッセージだ。
反撃の狼煙は上がった
もう映画の製作者(出資者や製作委員会)は、この表象問題に対し、傍観者ではいられないと悟るべきである。社会的少数者が安心して暮らせる世の中とは、娯楽やアートもすべて、その人たちをありのままに受け入れ、誰にでも常にオープンであるべきだからだ。新しいビジネスとしても、可能性を秘めていることが明らかになってきた今、マイノリティ俳優を積極的に起用することは、その作品にとってメリットしかないはずだ。
まずは大至急、セクハラ、モラハラ、パワハラを含む、犯罪行為、アンフェアな取引が横行しないよう、今すぐ社会へメッセージを出すことが、不可欠だ。それができない企業、団体は、松崎氏が繰り返し叫んでいるように、次世代の人材や観客からも、今後選ばれなくなることを知っておくべきである。
新しい価値観が生まれる時、多くの人にとっては霧のような、ノイズのようなものかもしれない。しかし、そのフォギーなノイズの中に新しい未来があると信じる。それは、たとえこの身の犠牲を払ってでも、勝ち取らなければならない未来だ。映画や舞台アートを目指す、マイノリティの人々が、そもそもスタートラインにすら立たせてもらえない、そんなエンタメ業界を捨て去り、壁の外でその才能と輝きを発揮し、自分たちの手で、健全な競争の場をつくりだすのだ。
「モザイクストリート」は、その狼煙である。
追記:ちょうど原稿をまとめていたころに、「コトブキ映画同好会」youtubeチャンネルにて、松崎氏による、忖度なしの映画業界のセクハラ、パワハラをぶった切る配信があったので、ここでも紹介したい。本当に面白いし、ためになる、勇気をもらう内容なので、映画関係者は必ず、見るようにお願いしたい。
本文:DEBO