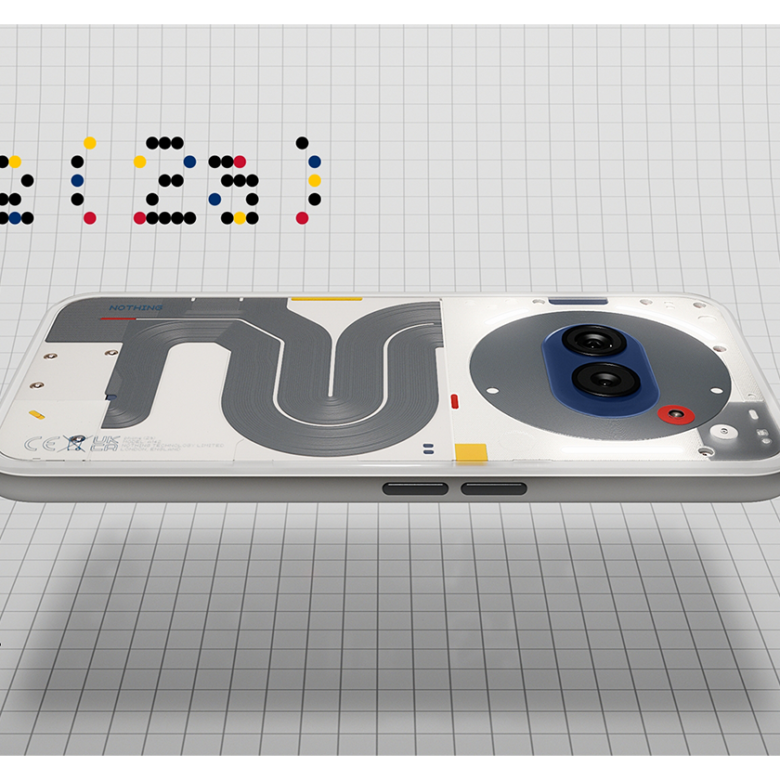WET LEG、キュートな歌声とポップな旋律にパワフルさもプラスされてとにかく最高な一体感!初来日東京公演ライブレポート

Wet Leg @O-EAST 2/15(WED)
グラミー賞2部門&ブリット・アワード2部門を受賞直後という絶好のタイミングでの初来日。イギリスのワイト島出身、デビュー・アルバムのリリースから1年足らずでワールドワイドな人気をまたたく間に獲得した彼女たちのジャパン・ツアーは、全会場ソールドアウトとなった。
膨れ上がったフロアは、もうこの距離とキャパシティで観られるのは最後かもしれない、という期待感が尋常ではない。リアン・ティーズデイルとへスター・チャンバースを中心に、ドラム、ベース、サイドギター/シンセのツアーメンバーを加えた5人編成のバンドは、アルバムと同じく「Being in Love」でこの夜のパフォーマンスをスタートさせた。シューゲイズ的繊細かつダイナミックなこのオープナーは、ウィットに富み遊び心に満ちたふたりの歌のイメージを覆す、ロマンティックな恋愛を客観的に捉えた内容で、たちまちシンガロングが起こる。

2曲目は「Wet Dream」。セクシャルなリリック、「一緒に家に帰らないか?/『バッファロー‘66』のDVDがあるんだ」と誘いをかけてくる鼻持ちならない男のセリフをコーラスに用いて晒すという痛快さが、疾走するグルーヴとともに開放感を与えてくれる。
リアンが「こんにちは東京、元気ですか?」とオーディエンスに呼びかけたあと披露したのは、ペイヴメントのような脱力したローファイ感漂うコーラスが癖になる「Supermarket」。アルバム中でもライブ映え間違いないと思われたが、向かい合ってギターを弾くリアンとへスターの姿には有無を言わさぬかっこよさがあり、観客の歓声がひときわ高まる。
アルバム中、へスターがメイン・ヴォーカルをとる唯一の曲「Convincing」をプレイしてくれたのもうれしかった。ドリーミーでサイケデリックなギターのトーンと繊細な歌声がマッチしたナンバーで、終始顔を隠しているシャイなイメージの強い彼女の魅力を再確認できる場面だった。

続いてアルバム未収録曲のスローな名曲「Obvious」。とかく皮肉っぽいユーモアという形容がされがちだけれど、挫折や絶望を経て「でも気にしない/ただやってみたかっただけ/私はナイフの背で人生を切り開いた」と驚くほど率直に歌うこの曲にこそ、ウェット・レッグの表現に通底するスピリットが反映されているのではないだろうか。
その静けさから一転、真夜中の空虚さをシュールに表現し、ざっくりとラウドなアンサンブルが音源よりもさらに凶暴さを増した「Oh No」は圧巻。バンドの90’sオルタナティブからの影響をあらためて強く感じさせてくれる。ブリッジでは自然と客席からハンドクラップが巻き起こり、フロアの一体感もさらに強まっていく。メランコリックな曲調で恋人との別れを詩的に表現したリリックが胸に迫る「Piece of Shit」の余韻も格別だった。
ファースト・アルバムが彼女たちのポテンシャルを完璧にパッケージしていたことにも驚きだが、リリース後のツアーの成果もあるだろう、クインテットのギターバンドとしての安定感が抜きん出ている。デヴィッド・ボウイ(あるいはカヴァーしたニルヴァーナの)「世界を売った男」のリフを引用した「I Don’t Wanna Go Out」に代表される、クラシックなブリットポップの系譜を受け継ぎながら、フレッシュに聴かせてしまう。レコーディングにおけるダン・キャリーと同じ役割として、サポートのジョシュ・モバラキのキーボードがアンサンブルの絶妙なスパイスとなっていることにも触れておきたい。

ボーイフレンドとのぎくしゃくしたやりとりが80年代ロムコムを観てるような「Ur Mum」。曲が始まる際にドラムのヘンリー・ホルムスが「君たちの力が必要なんだ」と宣言したように、後半リアンの「1、2、3…」の掛け声のあと、演奏が止まり、メンバーとオーディエンスが一斉にスクリームする。日頃の怒り・フラストレーションを吐き出す、なんとも爽快な瞬間で、自分たちの楽しみを追い求め、ため息も叫びも隠さずギターのノイズとともに増幅させる、ウェット・レッグらしい観客との感情の共有の方法だった。
大人になりきれない挫折と葛藤を瑞々しく描くジャングリーなギターポップ「Too Late Now」では、リアンとヘスターがターンしながらギターを鳴らす。ブリッジでの独白と「ただ泡風呂がほしいだけ」という切実さ、不器用な自分を祝福するこの曲にどれだけの人が救われただろう。

リアンが再度「ありがとう!」と客席に呼びかけ、どうしようもないパーティーを題材にしたエキセントリックな「Angelica」。アルバムよりもさらに轟音を増したアンサンブルに客席はカオスとなる。そしてラスト、「Chaise Longue」のモータリックなビートが鳴り響く。海外アーティストのライブでは珍しいくらい、全編にわたってフロアでシンガロングが起こっていたけれど、ひときわその声が大きくなる。誰もが生で体験したいと思ったに違いない、「Excuses me」「What?」のコール&レスポンスが場内に響き渡る。起伏の激しい、感情のジェットコースターに乗り駆け抜けていくような50分のセットはこの曲で最後となり、ギターのフィードバックノイズとともにステージを去った。主要音楽賞を総なめにし、歴史に名を刻んだ彼女たちによるメモリアルな一夜、と書けば格好つくのかもしれないが、いびつさを肯定し、’20年代に生きる20代の女性としての率直な感情をどこまでも自然体なまま描き世界を虜にした彼女たちにとっては「なにそれマジ!?」程度のものなのかもしれない。
Text by 駒井憲嗣
Photo by Kazumichi Kokei
グラミー賞2部門受賞&ブリット・アワーズ2部門受賞!