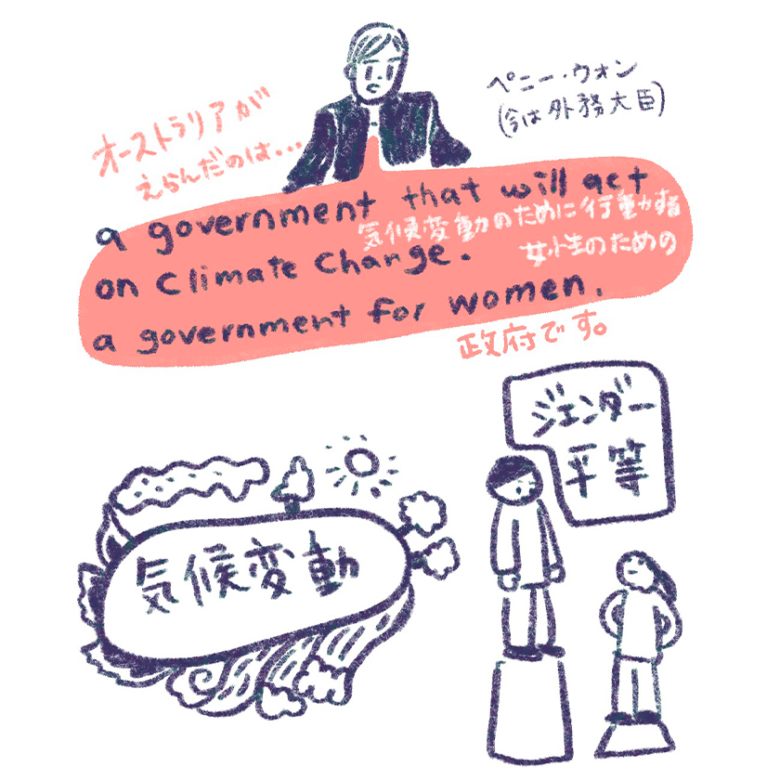日本のファンとの絆を深めた堂々のステージ。トム・ミッシュ、フジロックのライブレポート

パンデミックと過酷なツアーによってメンタルに不調をきたし、7月半ばに南半球ツアーをキャンセルしたトム・ミッシュ。あまりにも直前の出来事だったため、一時はフジロック出演も危ぶまれたが、相思相愛の関係を築いてきた日本のオーディエンスのために、彼は万全のコンディションで帰ってきてくれた。

最終日もいよいよ大詰め。ひたすら暑かった時間は過ぎ去り、今まさにクールな夜が訪れようとしていた。GREEN STAGEの天井にはミラーボールが吊るされ、ディスコ・ナイトを心待ちにする観客がどんどん集まってくる。
開演の19時を迎えると、不穏なノイズが鳴り響くなか、まずは6名のバンド・メンバーが登場。それぞれの音を合わせながら、焦らすようにジャム・セッションを始める。そこに主役のトムも現れると、ギターを巧妙に奏でながら「What Kinda Music」のイントロを紡いでいく。ヴァイオリンやパーカッションがしなやかに絡まり、サビのくだりでは突き抜けるようなハイトーンも披露。トムもバンドも出だしから絶好調だ。

そこからシームレスに、トムが「It Run’s Through Me」のリフを奏でだすと、待ってましたとばかりに拍手が沸き起こる。2018年のデビュー作『Geography』でブレイク後、ライブの経験をたっぷり積んできたからだろう。骨太のベースラインを軸としたグルーヴは、以前の来日公演よりずっと強靭なものになっていた。ベッドルームでの音楽制作をきっかけに成功を収めたトムは、いまや最大規模のステージを掌握するほどのパフォーマーとなった。
FKJとのコラボ曲「Losing My Way」のあとには、未公開の新曲「Falling for You」を披露。ディアンジェロ「Spanish Joint」を想起させる小気味良いグルーヴ、『In Rainbows』期のレディオヘッドに通じるギターの絡みが印象的で、エフェクトを効かせたトムの気だるげな歌声も含めて、トムとユセフ・デイズによる2020年のコラボ・アルバム『What Kinda Music』の延長線上というべきサウンドだ。
その後も、2016年リリースの初期人気曲「I Wish」で穏やかなアンサンブルを奏でたあと、『What Kinda Music』のリード・シングル「Nightrider」では艶やかに点滅する照明とともに、ダークな歌世界が繰り広げられていく。これまでの来日公演では『Geography』を軸にハッピーな雰囲気を演出してきたが、今回は『What Kinda Music』のヘヴィなトーンが加わったことで、持ち前のメロウネスを手放すことなく、ポジティブ一辺倒ではない深みのようなものが感じられるようになった。これもまた、トムが大きく成長した証だろう。

マイケル・キワヌーカとのコラボ曲「Money」ではゲスト・シンガーのジョエル・カルペッパーを迎え、トムのギターが歌声に柔らかく寄り添う。そしてまた、「Disco Yes」のリフが鳴り始めた瞬間に、エキサイトした観客がステージ前方へと押し寄せる。ミラーボールは七色に輝きながらまばゆい光を放ち、そこかしこにダンスの輪が広がっていく。ライブならではのロング・アレンジで、会場のボルテージも最高潮に達した。

「Movie」のチルタイム、ロイル・カーナー参加曲メドレー「Water Baby」~「Crazy Dream」を経て、『Tidal Wave』ではドラマティックな展開とともに、トムの官能的なギター・ソロが冴え渡る。最後は『Geography』から、「Lost in Paris」「South of the River」の二連発。誰もが体を揺らし、終始シリアスな表情をしていたトムも、このときばかりは会心の笑みを浮かべていた。上述のツアー中止もあって緊張していたのかもしれないが、こうしてフジロックで復活を遂げたことで、トムと日本のファンとの絆はますます深まったのではないだろうか。多幸感に満ちた70分だった。
文:小熊俊哉