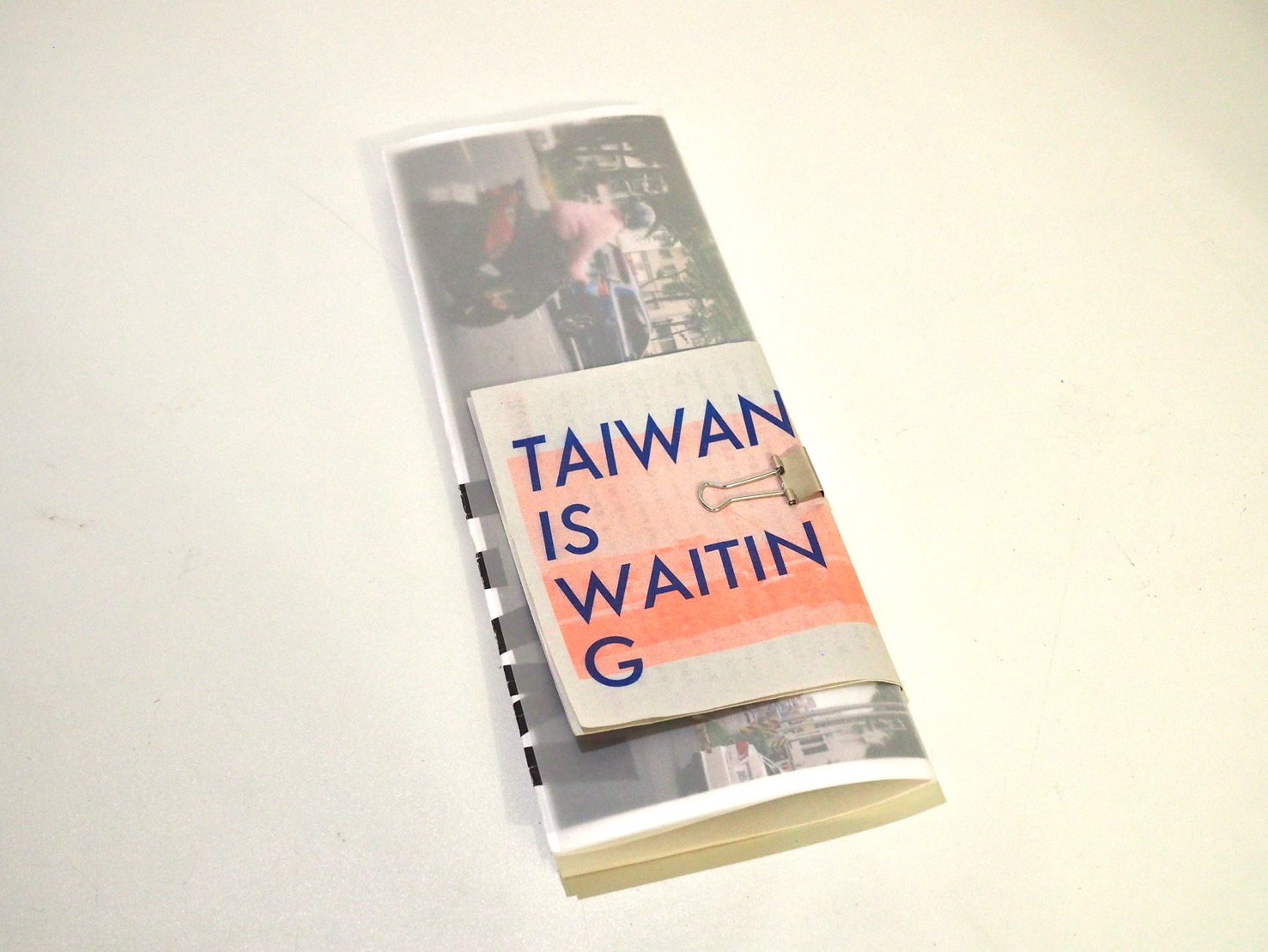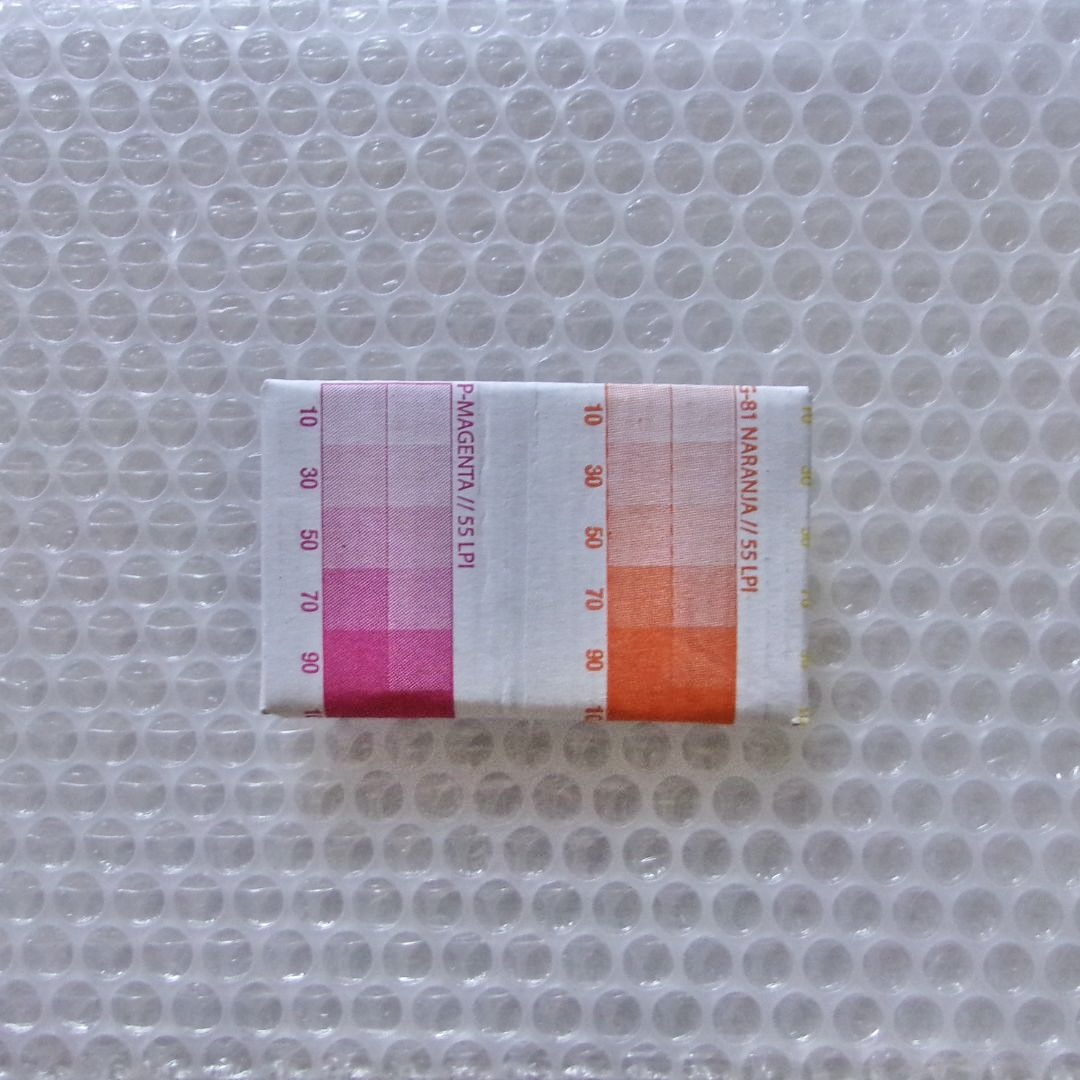数年前働いていた職場には、下は10代から上は60近くまで幅広い年代の人たちがいた。そのなかで私が特に仲良くしていたのは、40代の主婦たち。当時の彼女たちから見て娘ほどは若くなく、しかし上司である私に対し敬意と親しみを込めて優しく接してくれていた。たくさん一緒にお酒を飲んだし、たくさん愚痴も言いあって、彼女たちの存在に救われることが何度もあった。
それでも彼女たちの言動で気になることがひとつだけ。それは自分たちのことを「オバサン」と呼称すること。彼女たちは事あるごとに「オバサンだから」とか「ババアだから」とか、まるで息を吸うくらい自然に自虐を繰り返していた。最初こそあまり気にしていなかったけれど、何度もその言葉を耳にしていると、なぜ自分を卑下するようなことをわざわざ言うのだろうかと不思議に思っていた。
それから私は退職して海外で一年間過ごしたあと、久しぶりに彼女たちに会った。居酒屋のつるりとした畳に、ほとんどへたれた座布団でくつろぎながらビールを三杯ほど呑んだところで、ある違和感を覚えた。まるで巻き戻し再生されたかのように、同じ人が、同じリズムで、全く同じ愚痴を当時と同じように話していたのだ。私はその愚痴に曖昧に頷きつつも、内心ではまだ同じ話をしているのかと、彼女たちのあまりの変わらなさに少し居心地が悪くなった。そして久しく聞いていなかった「オバサンだから!」も鼓膜の中で強烈に響いた。英語には「オバサン」という単語とか概念がないからね。
思えば、何かを変えたくて海外へ行って戻ってきた私は、ある日は目の前の壁に真っ赤なペンキをぶちまけたくて、次の日には真っ赤になった壁をハンマーでぶち破りたくて、一体何を変えたいのかも分からずにとにかく必死で何かを変えようともがいていた。結局私は何を変えたかったのだろう? それは「日常」だったのだと、今になって思う。いつどんなときも刺激を欲していて、自分にできることは何かと自問自答を繰り返し、とにかく何かやりたくて、変わりたくて、少しでも前に進みたかった。常に体の内側にふつふつと煮え立つものがあって、私はその煮え立つものを自分でもどうすれば良いか分からず、時たま沸騰して溢れさせてしまうこともあった。その時は、それがぐらぐらと音を立て始める前に急いで目の前にあったビールを胃に流し込んだ。
それから五年近くが経ち、その間にはあらゆる人にとって異常ともいえる三年間があった。強制的に新しい、けれど同じ毎日を送らざるを得なくなり、毎日違う毎日を送るよりも毎日同じ毎日を送る方が、遥かに胆力がいるということを私は身をもって知った。自分の意思とは関係のない、自分以外の「何か」に生活を制限されることで溜まっていく心の澱には、まるで空気の薄いところで息をするかのような、うっすらとした息苦しさが混じっていた。
変えられないのであれば、同じ毎日をもう少し丁寧に生きてみることにした。すると、形も色も音もない愛おしさや、誰にも自慢できないけれどとびきりな尊さ、次の瞬間にはわっと消えてなくなる美しさが、繰り返す日々にしかと存在していた、していたのだ。私の前にあった真っ赤な壁がぼろぼろと音を立てて崩れ始めたとき、どこかで見たことのあるような、赤ちゃんを抱いた女の人が壁の向こうに見えた気がした。
思えば、彼女たちは私よりもうんと長く、同じ毎日を送ってきた先輩たちなのだ。出産を経て復帰した早々あーだこーだと文句を言いまくるオバサン。シングルマザーとして三人の子どもを育てるオバサン。幼稚園から呼び出されて二時間もしない内に強制帰宅するオバサン。旗振り当番を終えてから眠気眼で出勤するオバサン。ほとんど夜逃げして離婚を成立させたオバサン。ピークタイムに息子さんから「メントス買ってきて」とかわいいパシリの電話がかかってくるオバサン。仕事中に「もうすぐ上がるけど一応」と言ってポケットに入れておいた生理用ナプキンを落とすオバサン。職場から一歩出たあとの彼女たちのことを私は知る由もないけれど、でも確かに私は彼女たちの日常にいて、彼女たちの毎日を生きる強かさをいつも近くで見させてもらっていた。あの時、何も変わっていないと思った彼女たちは、ただそこに立っていただけなのだ。
そういえば、彼女たちが「オバサンだから!」と言うときは、いつも必ず笑顔だった。自虐だと思っていたそれは、淡々と繰り返す毎日を面白おかしく生きるための、あるいは自分を景気付けるための、ただのおまじないだったのかもしれない。そう思うと、彼女たちの「オバサンだから!」が不思議と無性に聞きたくなる。
私も少しずつオバサンに近づいてきている今日この頃、生暖かい春の陽気みたいに、少しそわそわしている。もしかしたら、私はオバサンに、彼女たちのようなオバサンに、早くなりたいのかもしれない。いつ、そのおまじないを背伸びせずに言えるようになるのだろうかと、そんなことを考えている。きっとそのうち無意識に、堂々と「オバサンだからっ!」と言う日が勝手にくるのだろうけど。そんなことを考えている間にも、彼女たちは今日も、きっと、昨日と同じ日を生きている。
文✒️:Chiba Natsumi