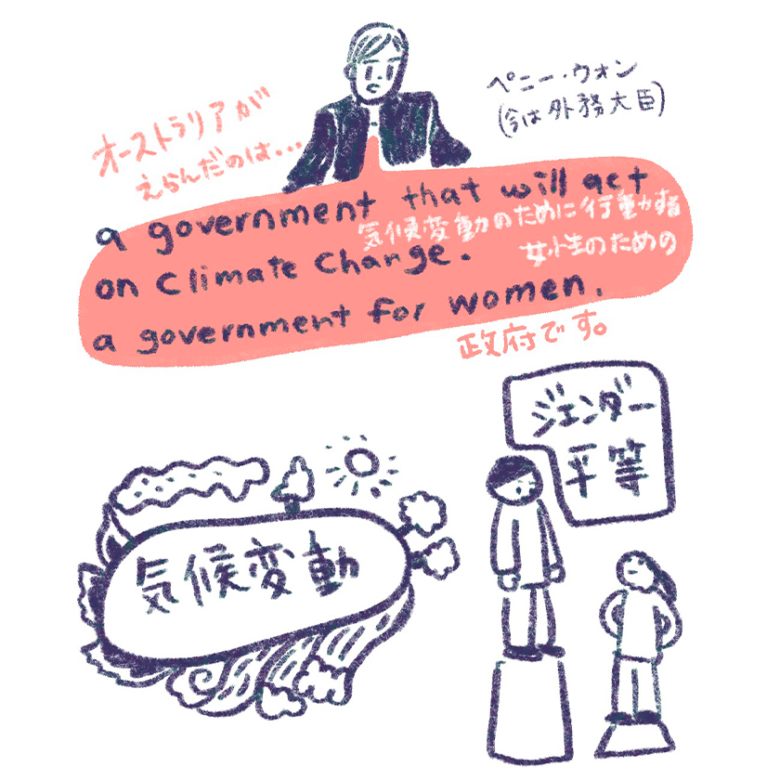『君の名前で僕を呼んで』原作レビュー~痛ましくも愛おしい傷を残してゆく、珠玉の物語
- col

映画『君の名前で僕を呼んで』が2月よりAmazon Prime Videoで見放題になった。これを記念して、原作となったアンドレ・アシマン著の同名小説について綴っていこうと思う。
物語の舞台となるのは夏の北イタリア。避暑に訪れた17歳の少年・エリオの元に、24歳の若手研究者・オリヴァーがやってきた。考古学教授であるエリオの父の研究を手伝うため、夏の間だけ居候するという。
何かに誘われると、すぐに「あとで!」と言って上手くかわすオリヴァーのことを、エリオは最初こそ好ましく思わなかった。しかし、次第に彼の思わせぶりな素振りやふと見せる仕草から目が離せなくなり、次第にオリヴァーについての思考が頭の中を占拠するように。両親の影響により芸術や教養に通じているエリオは、様々な芸術作品、また思想を引き合いに出して自分のオリヴァーへの感情を紐解こうと試みる。
「ほんとに大事なことについては、ほとんど知らないんだ」
どんなに世界の理や美しいものを知っていても、オリヴァーに対する感情の正体を言葉にすることが出来ない。ピアーヴェ川の記念碑の前で、ついにエリオはオリヴァーに自分の思いを口にする。そして自分しか知らない「僕の場所」へとオリヴァーを誘う。そこで静かに執り行われた、神聖とも呼べる無言のキス。
エリオとオリヴァーは、自分たちのことを静かに知っていき、そして「もう2度と取り戻すことのできない」夜を迎えるのだった。
「君の名前で僕を呼んでくれ、僕は僕の名前で君を呼ぶ」
これは物語の中で2人が初めて、心でも魂でも精神でもない、ふたつの実在する身体を交わらせた時、囁かれる台詞だ。
私はこれを呪い、と名付けた。自分は彼であり、彼は自分。似ているというより、そこに在るのは自分自身。互いの名前を互いのものではない身体で呼び合うことで、約束よりも強固で誓いというにはあまりに脆すぎるものが交わされた。それはこれから先、きっと自分たちはこの瞬間のことを一生忘れられずに生きていく、という呪いだった。
エリオは17歳であり、年齢に不相応な聡明さを持ち合わせていながらも、若さゆえの欠陥とも呼べる――、繊細で脆弱な部分、そして早熟な部分を同時に抱いた少年だ。オリヴァーに恋をしたこと自体、自分の感性や思想に今までにない心の高揚と合致を覚えるが、そこから逸脱し、その先の肉体的関係に進むことに躊躇いがなかった。対してオリヴァーは、彼と身体を結ぶことを躊躇した。最初の夜、部屋にはマリファナの匂いが充満していた。それだけの覚悟が無いとエリオと行為に及ぶことが出来なかったのだろう。
そうしてオリヴァーが言った台詞が、冒頭のものだ。
これは本当に呪いであり、覚悟だと思う。甘美な響きではあるが、この言葉には大いなる力が眠っている。「言葉にすること」、そして「それを相手のものと委ねること」。繋がりあった肉体もその一瞬だけではなく、感覚、触れられ方、余韻、匂い、すべてが2人の間で永遠に共有されることを意味した言葉だった。
「恋」というものは身体にさまざまな症状をもたらす。滑稽と思えることも、夢の渦中にいるかのような覚束ない思考で、どんなことも容易く行えてしまう。それを思考し、実行するのは肉体だ。肉体は精神より傷を負う。そして、そこに刻み付けられた余韻を、精神は忘れない。聡明なエリオはその恐ろしさに気づけないまま、オリヴァーとの短く鮮烈なひと夏を経験するのだ。
「僕は賢くなんかない。さっきも言ったろ。何も知らない。本は読むし、言葉のつなぎ方は知ってる――だからって、自分にとっていちばん大事なことをどう話せばいいかわかってるわけじゃない」
そんな彼が、オリヴァーの心臓を、匂いのついたシャツを求める。
ひどく感傷的に、ひどく人間的に。知性の塊が、原始的な恋をしているかのように。
「僕に残されるのは彼の心臓とシャツだけだったから」
ロマン派詩人のパーシー・ビッシュ・シェリーが残したエピソードを引き合いに、エリオはオリヴァーとの別れを思い、感情を言い残す。そして年月が過ぎ再会したオリヴァーが、同じことを自分に思っていたことが明らかになる。彼もまた、永遠に消えない傷を肉体に抱えていた。消えない傷を負った2人が再会を果たした時に交わす会話は色褪せないままに美しく、しかし確かな痛みを包含している。
第3部「サン・クレメンテ症候群」では、ローマの古書店で開かれたブックパーティーに参加した2人が、詩集を刊行した詩人、そして周囲の人間たちと交流する場面が描かれる。詩人は「サン・クレメンテ症候群」についてこう話した。
「日曜日の午後、家族や友人のために鼻歌交じりに炒め物をつくる私。(中略)互いに裸になって誰かと抱き合うことを渇望する私。ひとりきりになることを渇望する私。自分のあらゆる部分がそれぞれ時空を超えて離れたところに存在し、それぞれが私の名前を持っていると主張するときの私。そんなふうにいくつもの自分がモザイク模様をつくることを、私はサン・クレメンテ症候群と名付けた」
誰かと愛し合い、自分の肉体が彼もしくは彼女の一部と化したり、そのまま肉体が融け合って離別できなくなるのも、時空の中でかつての自分たちがひっそりと息をしているのも、サン・クレメンテ症候群だと私は思う。サン・クレメンテという建造物そのものが複雑な構成を成しているように、自分の他に自分がいると感じる瞬間、それもまた、サン・クレメンテ症候群だ。2人はこの症候群に苛まれたさなかで、真夜中に抱き合ったのである。
ローマの詩人が刊行した詩集の題は『セ・ラモーレ(もしも愛ならば)』だった。本当のところ、エリオとオリヴァーの間にあったのが愛なのかどうか、誰にも分からない。エリオは「堕落した少年」なのかもしれないし、オリヴァーは「冷たい青年」なのかもしれない。けれどふたつの肉体だけがあの日の痛みや疼きや、幸福を覚えている。
2人の人生がX点で交差する瞬間として、行為に及んだのは果たして本当に正しかったのだろうか。呪いじみた約束を交わしたあと、互いを愛おしいと思う激しさにより消耗し、傷を癒そうと2人でいた思い出を忘れ去ろうとする姿は決して幸福とはいえない。トーマス・ハーディの『恋の塊』がいうように、恋は決して喪失されない、痛ましく瑞々しい残滓を残していく。
「私は苦痛をうらやましいとは思わない。しかし、おまえが苦痛を感じているのをうらやましく思う」
エリオの父が、オリヴァーと別れた後のエリオに投げかけた言葉は何ものにも代えがたく優しいものだった。彼もまた若かりし頃、恋をしたことによる心の傷を負っていた。だからこそ、息子が覚えた離別による感傷に寄り添うことができたのだろう。
陽炎のような季節に互いの名前を呼び合い、呪われながらも一瞬を生きた彼らの姿は、私の心に深い余韻をもたらした。悲しみと歓び、そのどちらも痛みとして感じることのできる稀有な物語に触れられたことは、今までの読書体験でも類を見ない、素晴らしいひと時であったと感じる。
本作は映画化されており、作品はアカデミー賞脚色賞・作品賞・主演男優賞など多くの賞を受賞している。原作とあわせて、眩く忘れがたい恋に触れ、溢れる思いを巡らせていただけたらと思う。